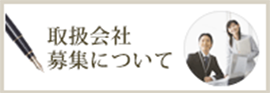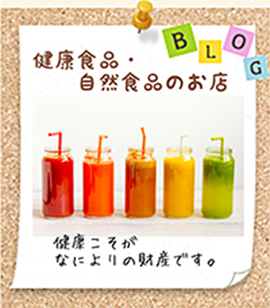健康ペディア
-
秋の味覚 さんまについて①

暑さ寒さも彼岸までといいますが、朝晩と過ごしやすい季節となりましたね。今回は秋の味覚の代表的な食材、さんまについてご紹介しますね。
さんまは漢字で書くと『秋刀魚』。形も色も刀に似ていて、秋に獲れる刀のような魚ということから名づけられたといわれています。
9月から10月にかけてが旬のさんまですが、栄養としては以下のようになります。 タンパク質と 脂肪 人が活動するのに必要な栄養。エネルギー源となる DHA 記憶力や集中力を高める成分。中性脂肪や悪玉コレステロールを減らす働きがある EPA 血小板の凝固を抑え、血液をサラサラにする働きや炎症を抑える ビタミンA 免疫や抵抗力を高める ビタミンD 骨や歯の材料となるカルシウムの吸収を助ける タウリン 肝臓強化に優れた効果を発揮する成分で、さんまの血合いの部分に多い 鉄分 赤血球中のヘモグロビンの合成に必要で、体の各器官に酸素を運ぶ働きがある
近年漁獲量が減少し、高級魚並みに高くなっていますが、栄養もたっぷりありますので是非食べて下さいね。次回、さんまを選ぶ時のポイントと効果的な食べ方についてご紹介しますね。
-
暑気払いについて

まだまだ暑い時期が続きますね。皆さんは、『暑くなったから暑気払いに行こう!』と誘われた事はありますか?暑気払いとは、その名の通り「暑さをうち払う」ために、体に溜まった熱を取り除くことです。海水浴や川遊びなどもありますが、ここでは、暑気払いに効く食べ物についてご紹介しますね。
◎麦(そうめん、冷麦、ビール)
冷麦やそうめんは暑い時期には食欲がすすみ、夏バテを防ぐにも効果的です。七夕は麦の収穫祝いも兼ねており、そうめんを食べると無病息災で過ごせるといわれてました。御中元、お盆の供物にそうめんを用いる理由のひとつは、暑気払いにも通じるからです。麦の収穫期は6月から7月。現代の暑気払いに欠かせないビールはまさに麦。体を冷やし、利尿作用で不要なものを体から出します。◎瓜(スイカ、きゅうり、冬瓜、にがうり、南瓜)
スイカやきゅうりは体の熱を下げて余分な水分を出してくれます。にがうりはビタミンCが豊富で夏バテ予防にもぴったり。冬瓜は冬までもつことからその名がつき古くから暑気払いに効く食べ物として重宝がられていました。南瓜は栄養豊富で糖質も多いのが特徴で保存性が高く、冬至に食べる風習も生まれました。このように瓜は総じて栄養価が高く、体力が衰える夏場には効果的なうえ、冬まで保存し健康維持に役立てることができます。◎氷(かき氷、氷菓子、氷料理)
冷たいものといえばかき氷。清少納言の『枕草子』に出てくるほど歴史は古く、平安貴族が暑気払いに食べていました。しかし、冷蔵庫がなかった時代、氷は貴重なもので庶民には夢の話でした。庶民には手の届かない氷に見立てて作られたのが「水無月」という和菓子で、三角形の葛の上に邪気払いの小豆をのせ、旧暦6月の禊の行事食になりました。今では誰でも食べられるかき氷ですが、夏ならではの風物詩です。◎甘酒
以前も甘酒については書きましたが、必須アミノ酸やビタミン、ぶどう糖やオリゴ糖などをたっぷり含み、『飲む点滴』とも言われる栄養ドリンクです。米を発酵させて作るノンアルコールの発酵食品なので、腸内環境を整える働きもあります。江戸時代には、甘酒売りが天秤棒をかついで売り歩き、夏の暑気払いに飲む習慣がありました。井戸水で冷やされた甘酒は、とても人気があったそうです。皆さん、今年の夏も体を冷やしながら栄養を蓄え、暑い夏に打ち勝ちましょう!
-
土用の丑とうなぎ

夏になると、スーパーの店頭に『土用の丑の日』のキャッチコピーと共に『うなぎ』が並びますね~。今年の夏の土用の丑の日は27日になります。特に夏の土用は、消化や栄養のことを考えた『食い養生』から、『う』の付くものを食べるようになりました。では、その中でも、なぜ夏の土用の丑の日といえば『うなぎ』というのが定番になったのでしょうか?
日本では7世紀から8世紀にかけて編纂された『万葉集』に大伴家持がうなぎを詠んだ歌があり、この頃からうなぎが滋養強壮に効く食べ物と知られていたようです。一般的にうなぎを食べる習慣が定着したのは江戸時代。平賀源内が知人のうなぎ屋から、夏はうなぎの旬ではないこと、蒲焼の味がこってりしている事から「夏に売り上げが落ちる」と相談を受け、店先に『本日土用の丑の日』と看板を立てたら大繁盛し、他のうなぎ屋もマネをするようになったと言われています。
うなぎの栄養価は高いといわれてますが、以下うなぎの栄養をまとめてみました。
タンパク質、脂肪 人が活動するのに必要な栄養。エネルギー源となります。
DHA 記憶力や集中力を高める成分
ビタミンA 免疫や抵抗力を高める成分
ビタミンB1 疲労回復と代謝を促す成分
ビタミンE 血管や肌の細胞の老化を防ぐ成分皆さん、今年の夏も土用の丑の日はうなぎを食べて、体調を崩さず夏を乗り切りましょう。
-
『1日1粒で医者いらず』 旬の梅を上手に取りいれよう!!

6月に入り、ジメジメとむし暑かったりして、体も疲れを感じやすい季節になりましたね。6月といえば梅雨。梅雨に入ることを『入梅』、梅雨明けすることを『出梅』といいますが、梅の実の熟す頃に雨季を迎えていたという事で、『梅』という字を使ったようです。
丁度、スーパーにもこの時期は青梅も出回り始め、梅酒や梅ジュース、梅ジャムや梅干を作る季節ということになりますね。今が旬の梅ですが、昔から『1日1粒で医者いらず』と言われるほど、身体に良いと言われる伝統的な健康食品です。梅に含まれている主な成分についてご紹介します。
◎クエン酸
酸っぱい成分で、唾液の分泌を促し、食べ物に含まれるカルシウムなどのミネラルや胃腸の消化吸収の効率を高めてくれます。強い殺菌力や整腸作用も
ありますので、夏の暑い時期に多い、食あたりや急性の下痢予防に効果が期待できます。
◎ポリフェノール、ビタミンE
体をさびにくくする働きがあり、血管や肌の細胞の老化を防いでくれます。この様に体の健康に良い梅ですが、梅干にして食べるとなると塩分が多く含まれているので、その場合は1日1粒までにして、摂りすぎに注意して下さい。
-
八十八夜とお茶の効能

5月に入り、暖かな陽気が続いてますね。今年は5月2日が八十八夜でしたが、皆さんも『♪夏も近づく八十八夜~』の歌いだしから始まる歌を聴いた事があると思います。歌に出てくる八十八夜はどういう意味があるのでしょうか?
八十八夜は雑節のひとつで、二十四節気の立春から88日目ををいい、春から夏に移り変わる節目の日、夏の準備を始める日、縁起のいい日とも言われます。農家では八十八夜を過ぎれば晩霜も終わり、気候が安定することから農作業開始の基準としています。文部省唱歌の『茶摘』がきっかけで八十八夜といえば茶摘みというイメージが定着しましたが、実際には茶摘の時期はその年の気候で異なります。
お茶の葉は冬の間に養分を蓄え、春になると少しずつ芽を出します。この時期のみずみずしいしい新芽を摘み取って作ったお茶が新茶(一番茶)で、それを飲むと長生きするともいわれています。新茶には、新茶ならではのさわやかさと高い香りがあり、その後に摘まれる二番茶や三番茶に比べてカテキンやカフェインが少ない為、苦味や渋みが弱く、旨味や甘みの成分であるアミノ酸(テアニン)が多く含まれています。テアニンには、脳をリラックスさせる効果があるそうです。二番茶、三番茶になるにつれ、お茶のテアニンは減少しタンニンが多くなってきます。渋味であるタンニンにも栄養はたくさん含まれています。タンニンについてはまた次回、ご紹介しますね。この様にお茶は、食後の一服には最適な飲み物ですね。風邪予防のために、うがいをするのも効果があるそうです。そしてビタミン類も豊富で美肌効果や老化防止にも役立ちます。特に日本茶に含まれているビタミンCは熱に強くあたたかいお茶でも効果が発揮されるそうです。毎日の食生活の中で、ぜひ旬の栄養たっぷりの新茶で季節を感じながら気分をリフレッシュして下さい。