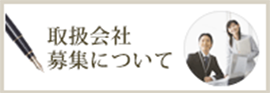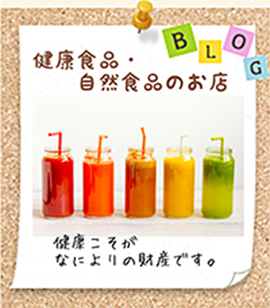健康ペディア
-
旬の食材

人間に性質があるように、食物にも味や効能などの性質があります。日本には四季があり、その四季に合わせた食材、そして最も味の良い時期が、“旬”というものです。
日本人が“旬”を言いはじめたのは、平安時代からだといわれています。朝廷の儀式で振舞われた季節の料理が転じて、野菜・果物・魚介類に限って、“旬”という言葉が使われるようになったといわれています。
旬といわれる食材には、夏なら体を冷やし、冬なら体を温めるというように、体にうまく働きかけてくれるものがたくさんあります。また旬の食材を使うと、おいしさだけではなく、栄養価も高くなるといわれています。それでは、春が旬の食材(3月~5月)を紹介していきます。
【野菜】
菜の花、ふきのとう、タラの芽、ニラ、春菊、かぶ、みつば、ワラビ、ゼンマイ、
うど、アスパラガス、筍、さやえんどう、新キャベツ、新玉ねぎなど
【果物】
はっさく、いよかん、あまなつ、デコポン、びわ、いちご、キウイ、マンゴー、
メロン、ライチなど
【魚介類】
サワラ、サヨリ、タイ、サバ、カマス、タチウオ、カワハギ、カツオ、サザエ、
ハマグリ、タコなど春が旬の食材は、ビタミン類、特にビタミンCやミネラルなどの栄養素が豊富です。野菜では、菜の花やフキノトウ、タラの芽やニラなど、春野菜は香りが強いものや芽物野菜が多く、これらには解毒効果や排出力が高いのが特徴です。
果物では、イチゴや夏みかん、キウイなどビタミンCが豊富な食材が多くなります。ビタミンCはお肌や体を元気にしてくれます。
魚介類ならあっさりして脂肪分が少なめの物が多く、冬に不足しがちなビタミンやミネラルを補ってくれます。
季節の変わり目は、気温の変化が激しくなり、体調を崩しがちになります。新年度の初めから体調を崩さないよう、この時期に必要な栄養素をしっかり取り入れて、毎日を健康に過ごしましょう! -
節分と大豆の栄養
2月3日は節分ですね。節分は季節の変わり目となる立春の前日です。旧暦では春から新しい年が始まったため、節分は大晦日に相当する大切な日で、新年を迎える為の邪気祓いが行われていました。その名残で『豆まき』が現在も各地で行われていますね。この『豆まき』で使われる大豆は、味噌や醤油、納豆など色々な形で日本の食卓を支えてきました。いわば日本のスーパーフードといえます。以前も大豆の栄養についてご紹介しましたが、主な栄養や効能について、再度ご紹介しますね。
・蛋白質:血液や筋肉などの体を作る主要な成分。酵素などの生命の維持にかかわる成分やエネルギー源にもなります。
・食物繊維:人の消化酵素では消化できない成分。便のかさを増やして腸の調子を良くしてくれます。
・脂質:体を動かす際のエネルギー源となる成分。体の生命維持に必要な必須脂肪酸であるリノール酸を多く含んでいます。
・マグネシウム:骨や歯の形成に必要なミネラル。神経の興奮を抑制したり血圧の維持などの重要な働きに利用されています。
・亜鉛:骨や肝臓、腎臓、筋肉に存在するミネラル。体の中の新陳代謝に関わる酵素の成分や蛋白質を合成する働きがあります。
・カルシウム:骨や歯などを作るのに必要なミネラル。他に止血作用や神経の働きや筋肉運動など生命の維持や活動に重要な働きがあります。
他にもカリウムや鉄分、ビタミンB群やビタミンEも含まれており、他の食材とバランスよく組み合わせるとより多くの栄養が効率よく摂れます。大豆は認知症予防効果が期待できるレシチン、生活習慣病予防が期待できるイソフラボンなども含まれる注目の食材です。是非、蒸し大豆や納豆、豆腐や豆乳などで、一日1回は大豆製品を使った献立を取り入れて下さいね。
-
みかんの栄養と効能で、風邪予防しよう!!

1月20日は大寒、一年で最も寒い日です。寒くなってきたこの時期、意識したいのは風邪予防。風邪をひきやすいこの時期、是非取り入れて頂きたい食材は“みかん”です。みかんは皮を剝いて手軽に摂取できるうえに、おすすめの栄養素をたくさん含んでいます。こたつで暖まりながら、おいしくみかんをほおばって風邪予防してはいかがでしょうか。
みかんの主な栄養と効能についてまとめました。
◎ビタミンC:
免疫力を高め、細菌やウイルスなどの抵抗力をつける働きがあります。又、悪玉コレステロールを抑制や美肌効果、鉄分の吸収をアップする効果もあります。
◎βークリプトキサンチン:
カロテノイドの一種。抗酸化作用があり、紫外線から皮膚や目を守る働きや骨粗鬆症予防、免疫力を高める働き、美肌効果もあります。
◎ヘスペリジン:
みかんの皮や袋、スジなどに含まれるビタミンです。血管を強くしたり血流を改善する働きがあるとされています。又、ビタミンCと共に血管を細菌やウイルスから守ってくれたり、ビタミンCの消耗を防いでくれる働きもあります。
みかんは一日3個くらいを目安に毎日食べるといいですよ。風邪で食欲がない時や固形物を受け付けない時は、みかんジュースにしてみると水分補給にもなりますので、是非取り入れて下さいね。
-
冬至の過ごし方

12月22日は冬至ですね。一年で一番夜が長く、太陽の力が一番弱まる日で、この日を境に再び太陽の力が甦ってくることから、昔の中国や日本では『一陽来復』という意味で『上昇運に転じる日』と言われてました。
冬至に食べる食べ物として親しまれているのは、冬至粥とかぼちゃです。冬至粥は小豆を入れたお粥の事で、小豆の朱が日本では魔除けの色と言われ、この日に食べる事で厄払いをします。小豆は以前もご紹介しましたが、食物繊維や小豆ポリフェノール、サポニン、カリウムなどのミネラル、ビタミンB群などの栄養が豊富に含まれていて、便秘解消や大腸がん予防、動脈硬化予防、むくみの解消や肌荒れ予防など様々な健康効果が期待されるうれしい食材です。かぼちゃを食べる風習は全国的に残っていますが、長期保存がきくことから冬の栄養補給として欠かせません。かぼちゃに含まれている主な栄養源はβ-カロテン、ビタミンCやビタミンE、カリウム、食物繊維です。風邪予防や動脈硬化予防、むくみの解消といった健康効果が期待される食材です。
冬至に柚子湯に入る習慣は昔からありますが、その香りや薬効で邪気を払い、体を清めるといった禊の意味があります。ゆずに含まれる主な栄養はビタミン類、カリウム、カルシウムですが、ほかにクエン酸などの有機酸類を豊富に含んでいます。その為、柚子湯に入ることで血行を促進して冷え性を緩和や体を温めて風邪予防、美肌効果が期待できます。
今年は寒暖差も大きいですが、柚子湯に入り、冬至粥とかぼちゃを食べて、冬を元気に過ごして下さいね。
-
実はブロッコリー、すごい野菜なんです!!~食べ方・料理編~

前回、ブロッコリーの栄養についてご紹介しました。今回、その食べ方、料理法をご紹介します。まずは、下処理。ブロッコリーの栄養を出来るだけ逃さない様に注意して下さい。
A)お湯で茹でる
①ブロッコリーを小分けに切って水で洗う。②沸騰したお湯に塩を入れて、短時間で茹でる(時間の目安は2分位、茎の部分が少し柔らかい位でOKです)。③茹でた後、水にさらさない。短時間で茹でる事と、水にさらさない事で栄養の流出(特に水溶性ビタミン)を防ぎます。
B)蒸し器で蒸す
温まった蒸し器に、小分けに切ったブロッコリーを入れて中火で約4分程加熱し、火を止めて蓋をしたまま余熱で蒸す(目安2分)。
C)電子レンジで蒸す
耐熱皿に小分けに切ったブロッコリーを入れてサランラップをして、3~4分加熱する。電子レンジは加熱ムラがでやすいので、少量を耐熱皿に平らに並べて加熱するのがお勧めです。
実はブロッコリーの栄養が一番多いのは、小分けにして残ったブロッコリーの茎と芯の部分。ブロッコリーは元々キャベツの変種なので、加熱するとキャベツの様な甘みがあります。硬い皮の部分を取り除いたら、味噌汁やスープの具材、炒め物に使ったりと捨てることなく使う事をお勧めします。
簡単なお料理をご紹介しますね。
~温野菜サラダ~
(材料)・ブロッコリー・人参・グリーンアスパラガス・サラダチキン・ドレッシング(お好みのドレッシングを使って下さい。出来ましたら、適量油の入ったドレッシングを使うことをお勧めします)
作り方は簡単!!①サラダチキンは、食べやすい大きさに切るか裂く。②ブロッコリー、人参、グリーンアスパラガスは食べやすい大きさに切って、蒸し器で蒸す。③ボウルに①と②を入れてドレッシングで和える。
適量の油は脂溶性のビタミン(β-カロテン、ビタミンA、D、K)の吸収し、ドレッシングに使っている酢やレモンなどの酸味は野菜に含まれているカルシウムや鉄分の吸収をアップさせる効果があります。是非、お試し下さい。