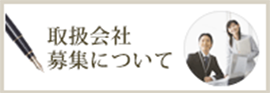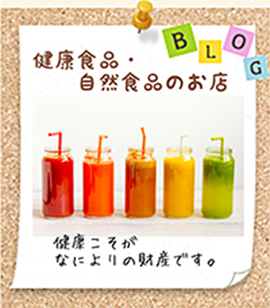健康ペディア
-
GWはワインを飲んでみよう♪

いつの間にか、4月も終盤に近づき、あともう少しでゴールデンウィークがやってきますね。
ゴールデンウィーク中は、日頃なかなか出来ない事をやってみようと思っている方も、きっと多いはず。私は、日頃まったく飲まない、お酒を飲んでみようと思っています。
せっかくなので、飲んで身体に良いものを!と思い、今回は、ワインと健康に関してお伝えします。
ワインはポリフェノールの含有量が多いので、適量であればワインを飲むと健康にも良いと健康番組などでも取り上げられますよね。
でも、ワインに含まれるポリフェノールってそもそも何?と疑問をもたれている方も多いのでは。
ポリフェノールとは、植物が紫外線の酸化ダメージから種子を守るために、葉や皮や果肉に含む色成分で、8000種類以上もあると言われています。
ポリフェノールと聞くと、赤ワインの原料となるブドウやブルーベリーなどの濃い紫色の色素を持つフルーツを思い浮かべる方も多いと思いますが、これはアントシアニンと言ってポリフェノールのうちの1つです。
中でも、赤ワインのポリフェノールの含有量が高い理由は、ブドウに含まれるポリフェノールの多さと、赤ワインの醸造法にあります。
ブドウは、果皮にアントシアニン、レスベラトロール、タンニンがあり、種子にプロアントシアニジン、カテキン、タンニン、ケルセチン、果肉にアントシアニン、果梗にタンニンとカテキンが含まれています。
赤ワインを醸造する際、果皮と種子と果肉と果梗(除梗する場合もあります)をすべて破砕してからタンクに漬け込んで果皮などから抽出される色素を果汁に移します。このときたくさんのポリフェノールが果汁に溶け込むから、赤ワインのポリフェノールの含有量が高くなるんです。
ワインのポリフェノールの効能は、ワインを飲む人間の体にとってうれしい作用をたくさんあります。
タンニンは、悪玉菌を減らす働きがあり下痢止めにも効果があります。更に、抗酸化作用を持ち老化防止や発がん抑制の効果もあるといわれています。
最近注目を集めているのが、ポリフェノールの一種であるレスベラトロール。
このレスベラトロールは、抗酸化物質でストレスへの耐性効果が強く、運動機能向上の効果が期待できるとされていて、夢の長寿薬かも!!!と注目を集めていたりします。
しかし!そんなうれしい効果がたくさんあるタンニンなんですが、実は摂りすぎると鉄分不足を招くおそれもあるんです。
タンニンは鉄イオンと結びつく性質があり、タンニンを摂り過ぎることで、体内でタンニンが鉄の吸収を妨げて、貧血を誘発する原因となることもあります。
何事も適量ですね。ワインは1日1~2杯が理想的な量ですが、私は、お猪口くらいごく少量から、はじめる事にしたいと思います。
最後に折角なので、ワインに合うお肉を1つご紹介します。
それは・・・ラム肉!
BBQテイストのラムチョップなんて、最高です!
普段食べているお肉の種類の中で、最も体を温めるといわれているラム肉。ガツンとパンチのあるスパイスを加えて一口パクリ。続いて赤ワインを一口ゴックン。想像しただけでヨダレが・・・。
皆さんもぜひ試してください!
By,CoCo
-
紫外線と上手におつきあい
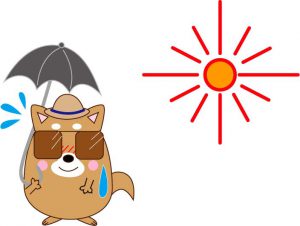
桜の季節も終わり、初夏の足音が聞こえてくる今日この頃です。
街中では、そろそろ日傘や紫外線防止の手袋を使う人の姿も見かけるようになりました。これから1年で最も紫外線の強い季節がやってきます。悪役扱いですが、紫外線(特にUV-B)は私たちの体に必要なものです。
皮膚がUV-Bを浴びると、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの生成が盛んになります。安眠、ストレス軽減等精神の安定に役立ってくれます。また、体内でビタミンDが作られます。
ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨の形成に役立ちます。そして、ビタミンDは、食物だけからでは必要量の半分しか摂取できません。UV-Bの力を借りて皮膚の下で作る必要がありますが、UV-Bは屋内までは届きません。
ここで日光浴の出番です。浴びすぎは体に悪い紫外線ですが、上手にお付き合いしましょう。
① 時刻は出来れば、正午前後まで。(午後は紫外線量が多くなります。)
② 木陰で10分程度でも効果は期待できます。
③ 乾燥・敏感肌の方は手のひらで日光を受けてみて下さい。
④ ガラス越しの日光浴は、皮膚の老化を促進するUV-Aを多量に透し、浴びたいUV-Bをほぼ完全に遮断してしまいます。おすすめしません。
⑥ 日焼け止めを使用した場合、その種類によってはUV-Bの吸収率は、5%まで低下するといわれます。日光浴のときは、日焼け止めは必要最小限にとどめ、後でお肌をケアしてあげることをおすすめします。
⑦ 毎日の食生活も気をつけましょう。せっかく日光浴しても栄養が不足したり、バランスがとれていないと心身の健康は得られません。
旬の食材を基本に、塩分・糖分・脂質の摂りすぎに注意しましょう。
by はっちゃん
-
コーヒーの効能

みなさんは健康診断の結果はどうでしたか?
私は・・・内緒です!さて4月は新生活も始まり、環境の変化も多い季節です。
身体は正直ですから、いきなりの変化に順応することができなかったりしてしまうことも…
そんな時にはコーヒーがオススメ!
今回はコーヒーの効能をご紹介しますね。①コーヒーポリフェノール「クロロゲン酸」の生活習慣病予防作用
コーヒーにはクロロゲン酸(コーヒーの苦味や渋味を作り出している成分)というポリフェノールが含まれており、クロロゲン酸には他のポリフェノール同様、抗酸化作用があるほか、中性脂肪が肝臓に蓄積するのを予防する効果や糖尿病を予防する作用があるといわれています。②クロロゲン酸とカフェインによるダイエット効果
コーヒーを飲むと自律神経の働きが促進され、脂肪の代謝が高まるといわれています。③クロロゲン酸の抗酸化作用による美肌効果
紫外線を浴びると肌が酸化して、シミ、しわ、たるみといったトラブルの原因に。コーヒーに含まれるクロロゲン酸には、酸化を予防する効果が期待できます。④カフェインによる覚醒作用・集中力アップ作用
カフェインには頭をスッキリさせ、集中力を高める効果があるといわれています。⑤カフェインの利尿作用で老廃物を排出する効果
カフェインを摂取すると、腎臓の血管が拡張し、血流が良くなります。血流が良くなると腎臓の働きが活発になって老廃物をろ過しやすくなり、老廃物を排出する効果が高まるといわれています。⑥コーヒーの香りによるリラックス効果
コーヒーの香りを嗅ぐと脳から出るα波(アルファ波)が増えるといわれています。飲み方は、1日カップ3杯、ブラックコーヒーを飲みましょう。
ブラックは苦くて飲めないという人は、酸味が薄く苦味が抑えられているものや、フレーバーコーヒーといってチョコレートやバニラ、ナッツなどの香りがついたコーヒーもあるので、色々な豆を試してみてくださいね。byあやや
-
朝食の役割

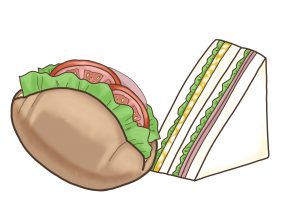
①脳を活性化させる
私達の脳は、ブドウ糖をエネルギー源として使っています。朝起きた時は、脳が使えるブドウ糖は殆どないので、朝食をきちんと摂ることで、脳にブドウ糖を供給し、脳が活性化します。脳が働き始めると、体もしっかり動き、集中力や思考力も高まります。
②体温を上げる
人の体温は、寝ている間に低下しています。その体温を上げるためには、朝食が必要です。消化管(口腔、食道、胃、小腸、大腸、肛門)は、筋肉でできているため、動き出すと熱を出します。朝食を食べることで消化管が筋肉運動をはじめます。 それにより得られた熱で体温は上昇し、身体は1日の活動の準備を整えます。
③便通がよくなる
朝ごはんを食べると、胃腸が刺激されて動き出し、排便されやすい状態になります。
【朝食の簡単おすすめメニュー】
<和食> おにぎり・味噌汁
おにぎりに鶏そぼろ・鮭フレーク・わかめなどを混ぜ込むと、手軽で、栄養価もアップ
<洋食> パン・野菜スープ
パンにハム・卵・スライスチーズなど、お好みの具材をはさむと栄養価もアップ
byニコ
-
花粉症対策(食生活)

桜の美しい季節になりましたね。ですが、花粉症の方には少々辛い季節です。4人に1人は患っているといわれる花粉症。生活全般を見直して、少しでも症状を軽くしていきましょう。
花粉症は花粉に対するアレルギー反応が発生する病気です。花粉症の場合、花粉が体内に入ると、花粉を異物として判断し、体外に出そうと、くしゃみ、鼻水、鼻づまりといった鼻の症状と、目のかゆみ、涙、充血といった目の症状を引き起こします。
しかし、人にはウイルスや細菌などから身体を守る免疫機能が備わっています。免疫力を上げ、抵抗力を高めることで、アレルギー症状の軽減が期待できるのです。
充分な睡眠、適度な運動、バランスの良い食生活をすることで、免疫機能が向上します。特に、免疫細胞の半分以上は、腸にあると言われ、腸内環境を良くすることで、免疫力の向上につながります。
では、どんな食材が花粉症改善に期待できるのでしょうか。
①発酵食品・・・ヨーグルト、納豆など
善玉菌を増やして、腸内環境の改善が期待できます。②ビタミンD、ビタミンEを多く含む食材・・・かぼちゃ、大豆、干ししいたけなど
免疫の調整に役立ちます。③食物繊維の多い食材・・・きのこ類、根菜類など
腸内の善玉菌のエサになります。④青魚・・・あじ、さんまなど
DHA、EPAがアレルギー誘発物質のヒスタミンの働きを抑えてくれます。⑤ポリフェノールを含むもの・・・チョコレート、甜茶、ルイボスティー、コーヒー
アレルギー症状を抑える働きがあります。身近なものから日々の生活に取り入れて、花粉症シーズンが終わってた後も続けてみてくださいね。
byサンコン