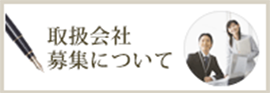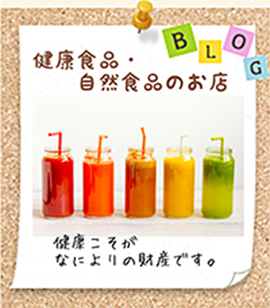健康ペディア
-
元気のしるし
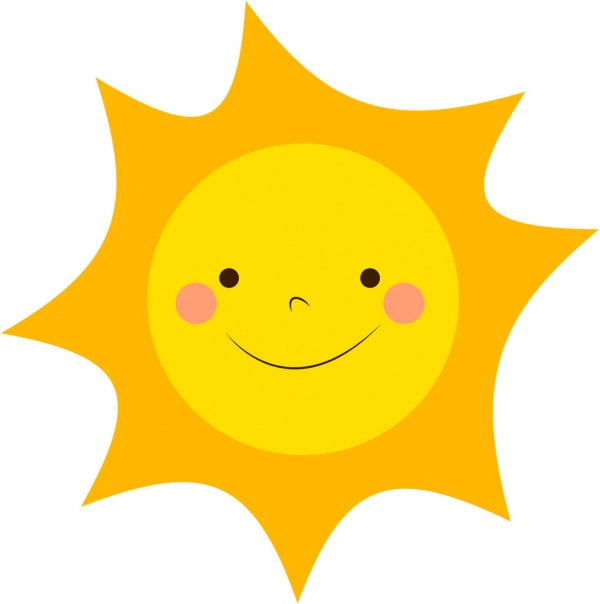
近年太陽の光を浴びる事について、日焼けやシワやシミなどの肌老化、また皮膚癌のリスクとデメリットばかりが注視されがちです。
ですが、日の光は健康に良い面もたくさんあります。1、体内時計を調整する。
太陽の光は不規則な生活や睡眠不足などで狂ってしまった体内時計を調整してくれます。
当たり前の事のようですが、生活リズムの調整には朝カーテン開け日の光を浴びる事からはじめましょう。2、骨を強くする。
ご存知の方も多いかもしれませんが、人も植物のように太陽の光でつくられるものがあります。
ビタミンDがその一つで、太陽の光に刺激され皮膚でつくりだされます。
この成分はカルシウムの吸収を促進し、身体を正常な状態に保つのに役立ちます。ビタミンDは食事などから摂取するのは難しいのですが、ほかのビタミンCなどと違い、
体内に蓄積することができる為、基本的には毎日太陽の光を浴びなければいけないということはありません。3、抗ストレス作用
朝、目覚めて太陽の光を浴びることで”セロトニン”の分泌が活性化します。
この”セロトニン”は神経伝達物質のひとつで、心のバランスを整える働きがあります。
そのため、これが十分に供給されないとイライラしたり落ち込みやすくなったりと
心のバランスが崩れてしまうといわれています。・目安は1日15分
季節によっても大きく変わってくるようですが、
目安は週に3回15分、日陰なら30分ほどのようです。
最初に述べたように日光浴にはデメリットもあります、浴びすぎにはご注意を。古くから太陽は元気の代名詞のように扱われているようですが、
昔の人も太陽が元気をくれることに、なんとなく気付いていたのかも知れませんね。 -
健康づくり30の法則

健康な生活のための「30の法則」というものがあるそうです。
ポイントは30分と30品目が目標だとか。その1
まず歩くことからはじめよう。
ひと駅前で降りて30分歩こう。
息がはずむ程度のスピードで歩け。
続けることが健康の第一歩。その2
バランスよく1日30品目を食べよう。
いろいろ食べても食べすぎは禁物。
脂肪は動物性、植物性をバランスよく。
塩分は控えめ、1日10グラム以下に。その3
30分早く寝てゆっくり休養。
30分早く帰宅してリズムをつくろう。
計画的に休暇をとってストレス解消。
家族や趣味を大切にしてリフレッシュ。健康のために
何事も意識して続けることが大切ですね! -
お酢を飲んで健康に!
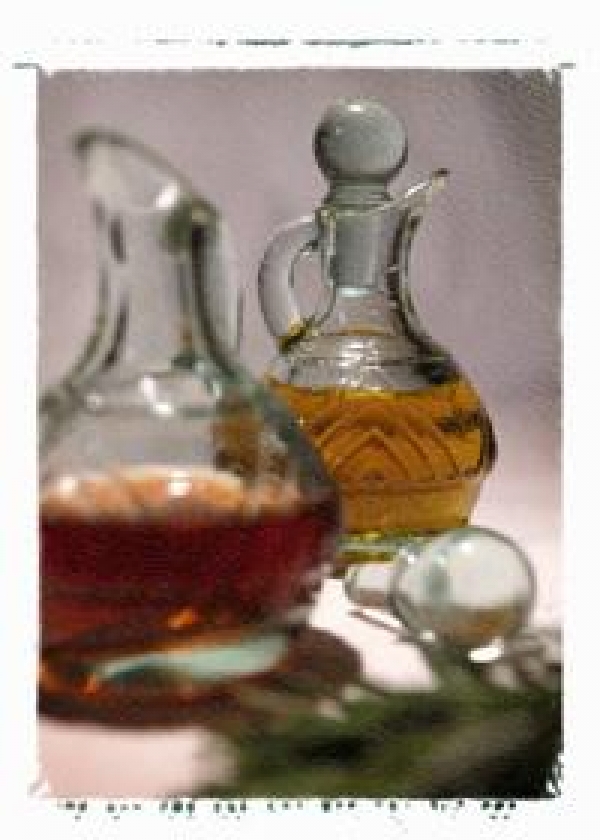
健康志向の高まりから注目されだした「お酢」人気の理由はやはりその手軽ですよね。
最近では、かなり飲みやすい「酢」も販売されていて、年々ニーズが増えているそうです。
では、酢にはどのような力があるのでしょうか。●食事から得たブドウ糖を無駄なく燃やしてエネルギーに変えることをクエン酸サイクルと言います。
お酢にはクエン酸自体は微量しか含んでいませんが、体内に入るとクエン酸に変化します。
クエン酸を摂取すると、クエン酸サイクルが活性化されて、新陳代謝が高まり、脂肪や老廃物が分解されて、
血流が良くなります。
このため、ダイエットや生活習慣病予防にも役立つと言われています。●臨床試験で、血圧を下げる効果あるこという結果も出たとのことです。
●悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やすと同時に皮下脂肪中に蓄積する中性脂肪を減少させる働きがあります。
●吸収されにくいといわれるカルシウムを一緒にとるとカルシウムの吸収率を高めます。
●お料理のときに塩分を少なめにして、お酢を使うと、味もぼやけずに減塩のお手伝いにもなります。
1日に必要な酢の量の目安は、15ml以上。大さじ1杯程度です。
お酢は原液で飲むと胃に負担がかかりますので、5倍以上に薄めて飲むことをおススメします。
個人的にお勧めはトマトジュースで割る!
トマトの臭みもなくなって思いのほか飲みやすいですよ。 -
トランス脂肪酸を避けた食生活を

昨今トランス脂肪酸が身体に悪いと言われていますが、そもそもトランス脂肪酸とは何なのでしょうか?
脂肪酸は脂質を構成している成分で、大きく分けると飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の2つに分類されています。飽和脂肪酸は乳製品や肉などに多く含まれ、不飽和脂肪酸は魚や植物油に多く含まれている成分です。不飽和脂肪酸の中にあって、トランス型の化学構造を持つものをトランス脂肪酸と呼びます。
もともと脂質は三大栄養素の一つであり、人間が生きていく為には必要不可欠な栄養素です。脂質の摂取量が少なければ、脳機能の低下や体温調節などに問題が出てきますし、摂りすぎると肥満や生活習慣病になる可能性が高まります。その為厚生労働省が、脂質はこの程度の量を摂るべきという目標量を示しています。どの栄養素にしてもそうですが、適量が大事ということですね。
脂質は適度に摂らなくてはいけないのですが、トランス脂肪酸は全く摂る必要がありません。トランス脂肪酸は、摂りすぎると善玉コレステロールを減らし悪玉コレステロールを増やす、動脈硬化の危険性が高まるなどのマイナス作用がある事が研究によりわかっていますので、トランス脂肪酸を含まない脂質を摂る必要がありますね。
商品によって差がありますが、一般的にトランス脂肪酸の多い食品は以下のようなものです。毎日の食事の中で、できるだけトランス脂肪酸は避けるようにしましょう。
穀類:クロワッサン、菓子パン、パイ、ポップコーンなど
菓子類:クッキー、ビスケット、ドーナツなど
油脂類:マーガリン、ショートニング、ファットスプレッドなど
乳類:コンパウンドクリーム、コーヒークリームなど
インスタント、レトルト、冷凍食品に多く含まれます様々な食品に含まれている為、むやみに神経質になることはありませんが、頭の隅に留めておいて摂取量を減らすように心掛けましょう。
-
大豆は健康の源

世界でも有数の長寿国である日本。世界的に健康への関心が高まっていることもあり、大豆・緑茶・魚・米などを中心にした日本食は世界各地でブームを起こしています。
中でも特に注目されている食材が『大豆』です。畑の肉とも言われる大豆は、タンパク質が30%もあり、アミノ酸組成も植物性タンパク質の中で群を抜いて優秀です。脂質も20%前後含まれており、オレイン酸、リノール酸等の必須脂肪酸を多く含んでいます。ビタミンやミネラルも豊富です。また、大豆イソフラボンや大豆サポニンなど多くの健康効果を持つ栄養素を含んでいることで注目を浴びています。
しかし、これだけ豊富な栄養素を含む大豆ですが、大豆は組織が非常に硬くて消化や吸収率が悪いという欠点があります。豆腐や納豆、豆乳など加工された食品は消化吸収が良いので、積極的に食べるようにしましょう。また、ビタミンCは含まれていないので、果物や緑黄色野菜などと食べるとバランスが良くなりますよ。